のどかから紹介いただいた、山ゼミ19期の洲濵 清晴です!
のどかさんには入ゼミ係や相談事などいつも本当にお世話になっております、、、、「哲学者」と呼ばれるのは非常にありがたいですが、そんな大した人間ではないです!
なるべくわかりやすくを心掛けましたが、伝えたいことが多すぎて結果的に読みにくくなってます。
こんなESではダメだよーという反面教師として読んでいただければ幸いです!
(ブログとは違い面接やESでは制限があるので、伝えたいことに優先順位をつけて数を絞ることも大事です!)
ESについてはのどかさんが前回のブログで非常にわかりやすく書いてくれているので、そちらもご参照ください!
↓今回のブログのアウトラインは以下の通りです。
- 自己紹介
- ESについて
2.1 ESとは「ただのコミュニケーション」
2.2 ES作成時3つのポイント
- 最後に
1.〈自己紹介〉
名前:洲濵 清晴
出身:島根県(珍しい)
バイト:羽田空港カフェ・バー
係:入ゼミ
趣味:カフェ巡り、散歩、旅行
自然に囲まれた島根の山奥で育ったので、自然がないと生きてけません!
都内でも「自然を感じられる場所」を求めてカフェ巡りをしています。旅行も趣味で、2年生の春休みにはヨーロッパ半周してきました!国内旅行も好きなので、おすすめスポットあったら教えてください~

2.〈ESについて〉
2.1 ESとは、ただのコミュニケーション
みなさんはこれまでにESを書いたことがありますか?もしかしたら書いたことが無くて「何を書けばいいのかわからない!」って方もいらっしゃるかもしれません!
でも、ESは小難しいものではありません。要は” 自分を事前に知ってもらうためのコミュニケーションツール”です。つまり、面接を文章でやっているようなもの。面接と違ってしっかり事前に考えられるので、むしろこちらの方が準備しやすいかもしれないです!
面接官も「この人の良さは何だろう」「一緒に学んだらどんな感じだろう」とポジティブにみています。だからこそ無理してよく見せる必要はありません。自分を理解して、自分の言葉で表現することが大切です。
2.2 3つのポイント
基本的にESには設問があり、それぞれの設問に答えていただければいいと思います。ESの書き方についても、ネットで検索していただけると出てくるので参考にしてみてください。今回は、特に重要だと思うポイントを3つに厳選してお伝えできたらと思います。
ポイント➀「適切なコミュニケーションがとれているか」
ESは文章形式のコミュニケーションです。各設問に対して適切に答えられているかどうか注意してください。
簡単じゃん!と思うかもしれませんが意外とできていないものです。山ゼミのESは記述量が多いので、書いている途中で何を書いているのか分からなくなってしまうかもしれません。
慣れていないうちは書く前に予め構成を考えたうえで書き始めるのがいいでしょう。
ポイント➁「読みやすい文章かどうか」
ESはコミュニケーションです。読みやすさは適切なコミュニケーションでもあります。
自分が読みやすいと思う文章は、「➀結論ファースト➁文章のつながりが適切である③一文が長くない」この3点を満たしているものです。
1.結論ファースト
口酸っぱく聞くフレーズかもしれませんが非常に重要です。
結論ファーストのメリットは、
- 第一に読み手が内容を理解しやすくなること
- 第二に書き手の伝えたいことがしっかり伝わること
初めに結論を伝えることで、読み手は全体の方向性を理解しやすくなります。
物語を読むときに、題名やあらすじがあれば理解しやすいのと同じです!
2.文章のつながりを意識する
前後の文章がつながっているかどうか確認してみてください。
つながりのない文章は、読み手が「ここはこういう意味かな?」というように自分なりに文章を補完する必要が出てきます。それより読み手の負担が大きくなります。
また、読み手に補完をさせてしまうと書き手が伝えたいことが伝わらない可能性があります。読み手に「解釈の余地」を残さないように意識してください!
3.一文を短くする
長すぎる文章は読みにくく、伝わりにくくなります。短ければ内容がスッと入ってきます。(この章は他よりスッと入ってくるはず!)
上記3つのポイントを抑えてもらえると読みやすいESを書けると思います!
自分以外の人に読んでチェックしてもらうのもおすすめです。
ポイント③「熱意が伝わるか」
これまでは形式などの注意点でしたが最後に内容についてアドバイスです!
形式も大事ですが、最終的には「熱意=情報量」です。
ESや面接では、「この人と一緒に山ゼミで学びたい!」「山ゼミに入っても頑張ってもらえる!」と面接官を思わせればよいわけです。そのためには自分がいかに山ゼミを志望しているのか、その熱意を情報で裏付けることが重要です。
熱意とはどのようにして測ることができるのでしょう。熱意は情報を集めることで生まれます。「山ゼミに入って○○を身につけたい」そう語るためには必然的に山ゼミの情報が必要です。
Instagram、ゼミ員ブログを見て、「どんな活動があるのか、先輩たちがどんな志望動機だったのか、自分は山ゼミに入って何をしたいのか、どんな人間になりたいのか」これらを語れるくらい情報を集めるといい気がします。
自分は昨年、三田祭の展示やオープンゼミにも参加しました。オープンゼミでは教室が閉まるくらいまで質問しまくってました、、、、!
「明確に○○したい!」と語れるためにも情報を集めることが重要だということをもう一度伝えておきます!
もちろん情報を集める中でやっぱ山ゼミは違うかも、他のゼミのほうがいいかも、、となってもいいと思います!ミスマッチをなくすことも選考では大切です。選ばれる立場でありながら、選ぶ立場であることを忘れないでください!
(ポイント➃)自己理解はできているか
これはESというよりかは選考全体でのアドバイスです!なので、読み飛ばしちゃっても大丈夫です~
無理して魅力を伝えなくていいと思います。ESや面接、一つ一つの仕草を取ってみても、自分はこんな人間だよ~と自分の特徴を相手に伝えることができれば十分です。ちなみに自分は自己肯定感が低いためか、自分の特徴は語れますが魅力は語れません(泣)
限られた時間の中で自分がどんな人間か語れると、面接官にとっては判断材料が増えます。(伝えきれなくても面接官が可能な限りくみ取るので安心してください!)
自己理解を深めるには?
「自分がこれまでどんなことをしてきたか」「なぜ行ったのか」「そこから何を学んだのか」これらを考えてみると自分がどんな人間かみえてくるかもしれません。
選考は共に学びたい人を選ぶためのものです。本来は時間をかけたいですが面接官は限られた時間の中で勝手に皆さんの良さを引き出そうとします。「魅力は何だろう、入ってくれたらどんな感じだろう」こんな風に思いながら面接をしています。
面接中は敵のように見えるかもしれませんが、決して敵などではないです。落としたい!だなんて一ミリも思っていないのでそこは安心してください。
だからこそ、「自分ってこんな人間だよー山ゼミとマッチしてる?」これくらい気楽に来れるように、面接の準備ができているといいと思います!

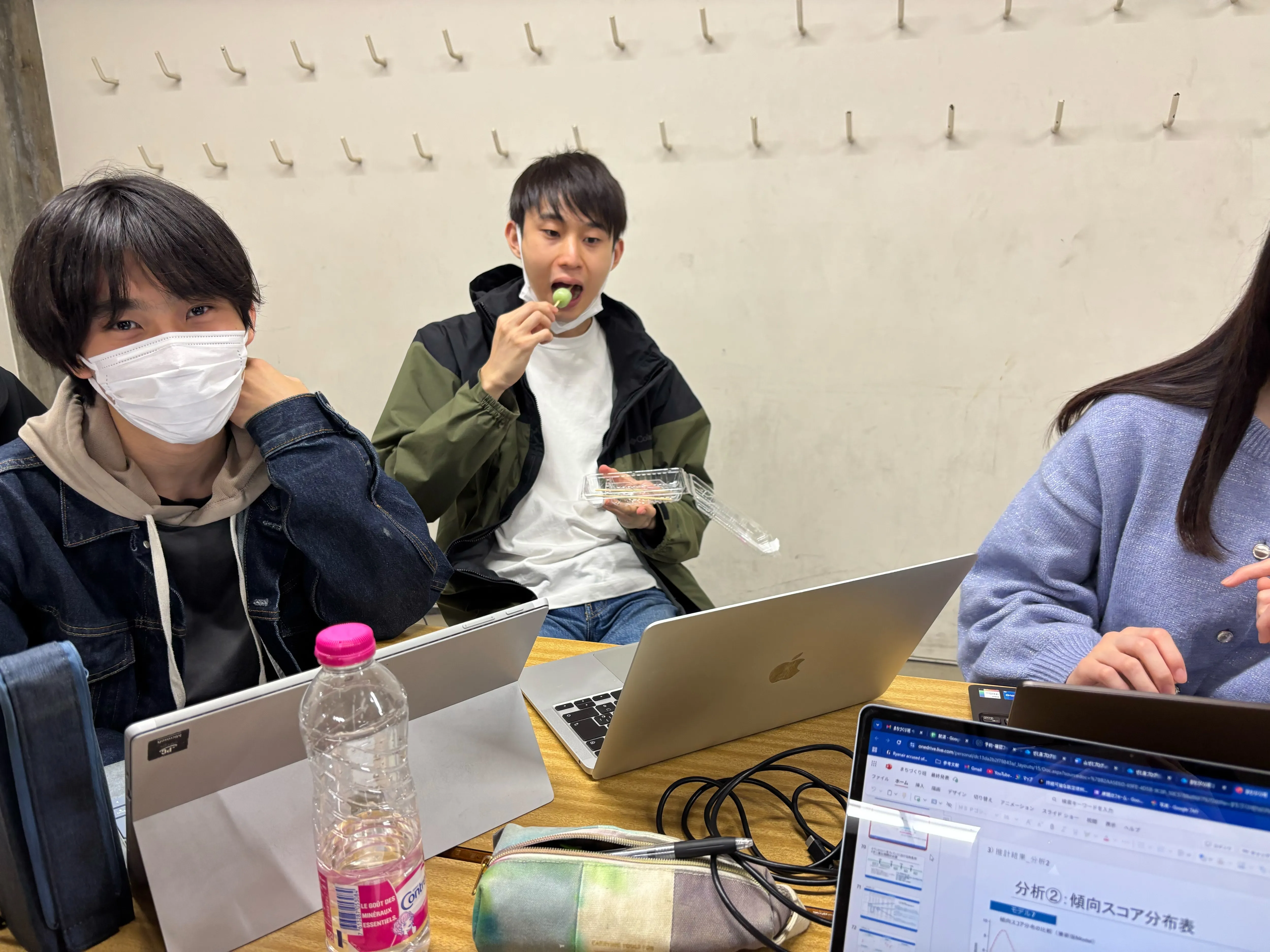
3〈最後に〉
沢山情報を集めたうえで比較検討し、本当に入りたいと思えるゼミに入ってください!自分はゼミに所属してしまっているので、ゼミをおすすめする立場ではありますが、他の道を選ぶことも素晴らしいと思います!
ただ一つだけ言えるのは、たくさんの人と関わり、もまれてください!
そうすれば、自分がどんな人間かわかりますし、今後の生き方も分かってくるかもしれません。
ゼミ選考は緊張すると思います。落ちちゃったらどうしよう、心配になると思います。
皆さんの良さを全力で受け止めるので、全力でぶつけてきてください!そして何より楽しんでください!
次回予告
次回のブログは田嶋玲が「面接について」書いてくれます!
入ゼミ係が一緒で、いつも核心を突くアイデアや、最後に決定するときに重要な示唆を与えてくれることがめちゃ多いです!自分は選択肢を出すことはできますが、そこから絞ることが苦手なのでいつも助かってます!
実は田嶋玲とは面接が同じで、この方はなんで緊張してないんやろうか、、、と驚かされたのを覚えています。そんな田嶋玲なら、なにか秘策を教えてくれるはずです~

ゼミ説明会後に語り合った公園です~後ろ姿が田嶋玲です!笑